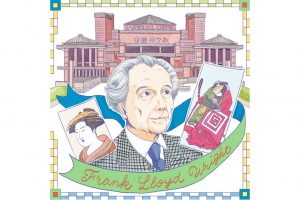心地よく語りかける繊細な音楽
19世紀前半のイタリアでは、ロッシーニやドニゼッティの作品のような、英雄的な人物や絶世の美女が登場し、低音から高音まで均一に美しく発声する「ベルカント・オペラ」が主流だった。しかし、19世紀後半には物語や歌唱にドラマ性を重視し、市井の人々の恋愛模様や死を舞台上で明確に表現する「ヴェリズモ・オペラ」が登場した。プッチーニはマスカーニやレオンカヴァッロとともに後者に位置付けられるが、彼ならではの繊細で優雅、叙情的な音楽は、ショッキングな内容を和らげ、受け入れやすいものになっている。
作品のためには信念を曲げない
プッチーニは「劇場のために作曲することを神に命じられた」と自認していたこともあり、オペラの制作に関しては題材の選定から舞台効果に至るまでこだわり抜いた。特に「いい台本がなくては私の音楽は成り立たない」と台本を重視していたため、台本作家へ何度も細かい注文を出すことが常で、対立することもしばしば。出世作『マノン・レスコー』(1893年)には台本に5人もの人物が関わった。最終的に台本を担当したのが、文学界で高名なジュゼッペ・ジャコーザと、地方色と史実の綿密さに定評のあるルイージ・イッリカ。さまざまな舞台設定に対応できる教養のある2人とは、代表作の多くを共作し、「黄金トリオ」として長く関係が続いた。
遺作となった壮大な愛のドラマ
古代北京を舞台にした『トゥーランドット』は、美しき皇女トゥーランドットが異国の王子カラフの想いに触れ、真実の愛に目覚める物語。未知の国の音楽を取り入れるため、中国産オルゴールや音楽辞典を参考に制作を進めていたが、プッチーニは作品が未完のまま、1924年に喉頭癌で死去してしまう。ラストシーンは、オペラ作曲家フランコ・アルファーノが補作して完成させた。1926年、ミラノ・スカラ座での初演の際には、プッチーニが作曲した最後の箇所で指揮者のトスカニーニはタクトを置き、“Qui il maestro finí.”―「マエストロ・プッチーニはここで作曲を終え、亡くなりました。」と言い演奏をやめた。
この作品の面白さの一つが、補作者や演出家によって物語の解釈が異なること。さまざまな公演を見比べてみたい。
<完>