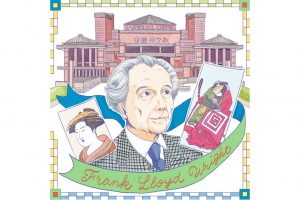人生のターニングポイントとなった「ハイリゲンシュタットの遺書」
20代後半から聴覚障害に見舞われたベートーヴェンは、31歳の頃に田舎のハイリゲンシュタットで半年間ほど静養することに。しかし回復の兆しがみられず死を決意する遺書をしたため、絶望の淵にあっても芸術の存在が自分を救ってくれたという心情を吐露。これ以後、耳が悪いことを知られても構わないとばかりに、周囲の目を気にすることがなくなり、音楽の歴史に革命を起こす作品を手掛けていく。ちなみに遺書は、弟に充てたものであったが、死後に発見され、文章からは彼の粘り強い性格も垣間見えるのだが、まさにベートーヴェンの音楽そのものなのが実に興味深い。
歌のない器楽曲(インストゥルメンタル)に、物語を持ち込んだ「標題音楽」の先駆者
曲名として、情景が浮かぶような言葉を付けるのが現在では当たり前のことのように思われているが、18世紀までは歌詞がついていない作品は「交響曲」等といった即物的なタイトルを選ぶのが常識。ベートーヴェンは交響曲第6番に《田園》という副題を付け、更に各楽章にもどのような情景を描いた音楽であるか分かるような言葉を添えた。この試みから後にベルリオーズの《幻想交響曲》や、リストの交響詩が誕生。歌詞がない音楽で物語を伝える、いわば映画音楽の先祖となるような分野が生まれたのだ。
ベートーヴェンと日本
クラシック音楽が日本に輸入され始めた明治・大正時代には、ベートーヴェンは数いる有名作曲家のひとりに過ぎなかった。ところが没後100年を迎えた1927年に偉業が称えられる機会が数多く設けられたことで、人生の困難に打ち克って業績を遺した偉人というイメージが流布。その結果「楽聖=音楽の聖人」と呼ばれるまでに。とりわけ日本人に馴染み深い「第九」は、12月だけで200回ほども全国で演奏され、そのうち8割はアマチュア合唱団によるもの。日本人にこれほど愛されているクラシック音楽は他にない。
<完>