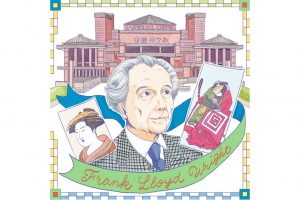子供の頃から絵画好きだった漱石は、イギリス留学中にも美術館へよく足を運び、そこで感銘を受けたターナーの風景画や、グルーズの憂いを帯びた女性像などのイメージは、後の小説の端々で印象的なモチーフとなった。後半生は自ら筆を取って絵画に打ち込むようになり、その絵は漱石を慕う門人たちの間で人気を呼ぶ。随筆家の内田 百閒(1889-1971)も、漱石の絵を人づてに入手し、立派な表装をして自宅に飾っていた一人だったが、ある日それを見た漱石から描き直しの申し出があり、新しい絵と交換。古い絵は「人に見せたくない」と破かれてしまった。漱石の生真面目な一面が伝わる逸話である。
夏目漱石〈後編〉
アーティスト解体新書
No.013
日本近代文学を代表する作家、夏目漱石は、多忙な執筆のかたわら西洋の美術・音楽などさまざまな趣味を楽しみ、周囲には彼を慕う多くの門人が集まりました。多彩なエピソードからはチャーミングな一面も顔をのぞかせます。
イラスト:豊島宙
構成・文:TAN編集部(合田真子)
夏目漱石(なつめ・そうせき 1867-1916)
本名・夏目金之助。江戸の牛込馬場町下横町(現・東京都新宿区喜久井町)生まれ。東京帝国大学英文科を卒業後、旧制高校や大学で英語教師をしながら英文学研究に取り組むが、明治38年(1905)、俳句雑誌『ホトトギス』に寄稿した『吾輩は猫である』が評判となり、小説の道へ進む。

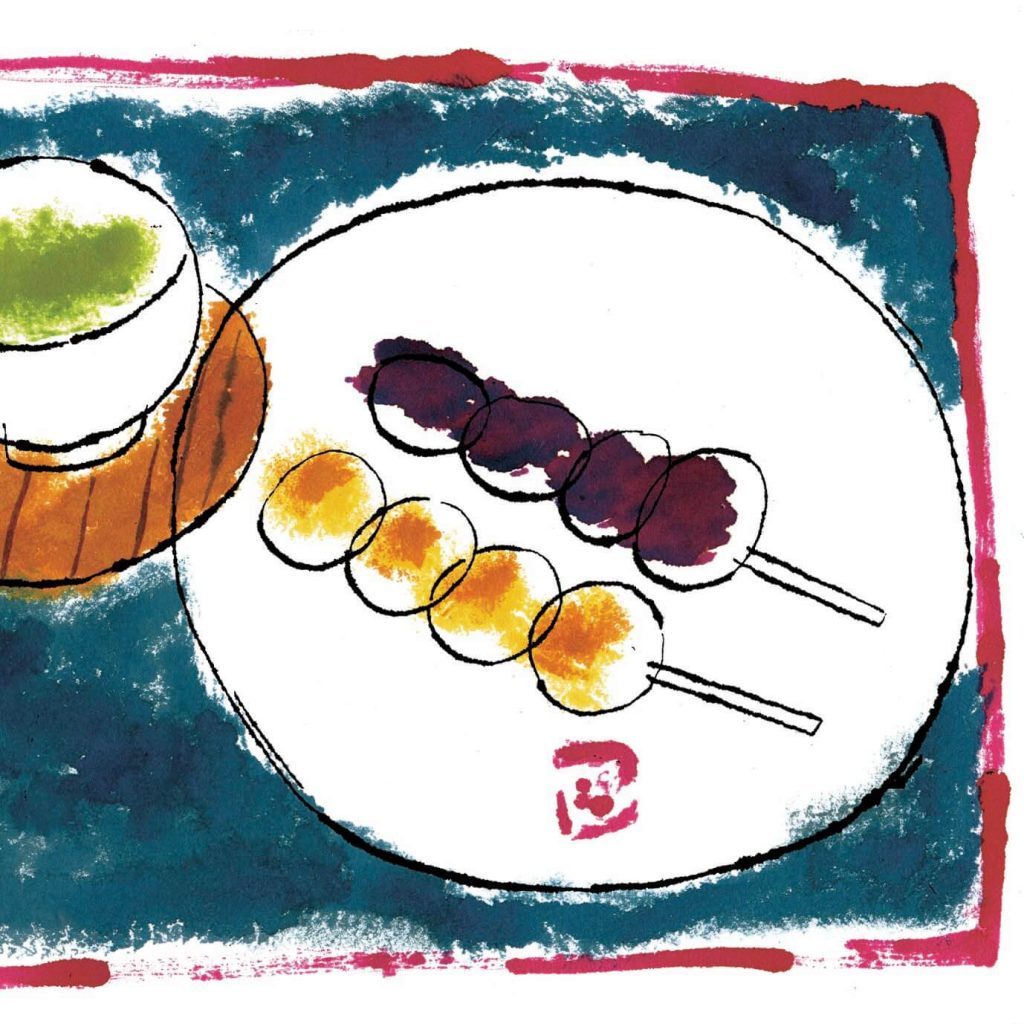
酒は猪口一杯程度しか飲めなかったものの、食全般への興味は旺盛だった漱石。特に目がなかったのが甘いもので、作品のなかにも『吾輩は猫である』の羽二重団子や最中、『坊っちゃん』の笹飴や道後温泉の団子、『三四郎』の栗饅頭など、漱石の好物の甘味がたびたび登場。とりわけ『草枕』の「青い練り羊羹」が青磁の皿に盛り付けられた光景の記述は、名文として知られる。後半生、度重なる胃炎と糖尿病に悩まされながらも、砂糖衣の落花生がやめられず、健康を心配した鏡子夫人に隠された羊羹を幼い娘に探し出してもらい、こっそりと楽しんだ。

義太夫や謡などの邦楽を好んだ漱石に西洋音楽を手ほどきしたのは、漱石の門人で、物理学者・随筆家の寺田寅彦(1878-1935)といわれる。時を前後して明治23年(1890)、西洋音楽の生演奏が聴ける施設として東京・上野に東京音楽学校(現・東京藝術大学)の「奏楽堂」が完成。ここで催される演奏会に寺田は漱石を頻繁に誘い、漱石も楽しみに通った。その見聞の数々は、小説『野分』などでいきいきと描かれている。ある演奏会で、蛙の鳴き声やシャンパンの栓を抜く音が楽器で再現されたのを漱石はひどく気に入り、帰り道でもその口真似をしてごきげんだったという。
〈完〉
豊島宙(とよしま・そら)
イラストレーター。1980年茨城県生まれ。パレットクラブスクール卒業。
国内外問わず、雑誌、広告、WEB、アパレルを中心に活動中。サッカー関連のイラストレーション、メンズファッションイラストレーション、似顔絵を得意とする。