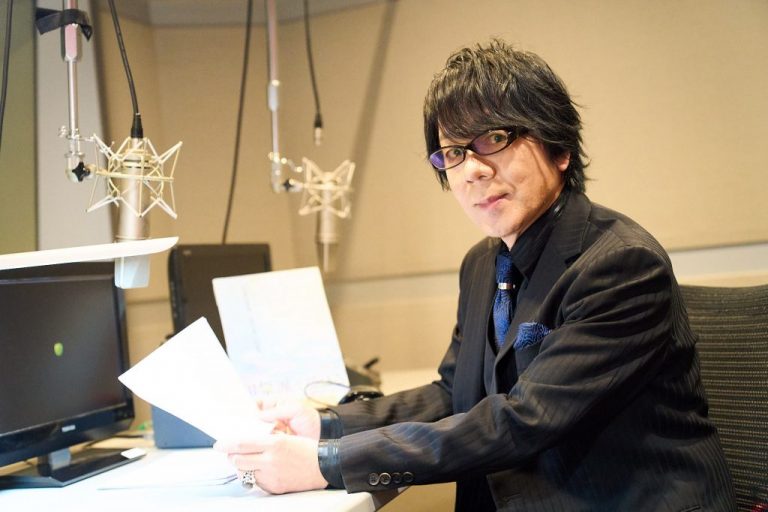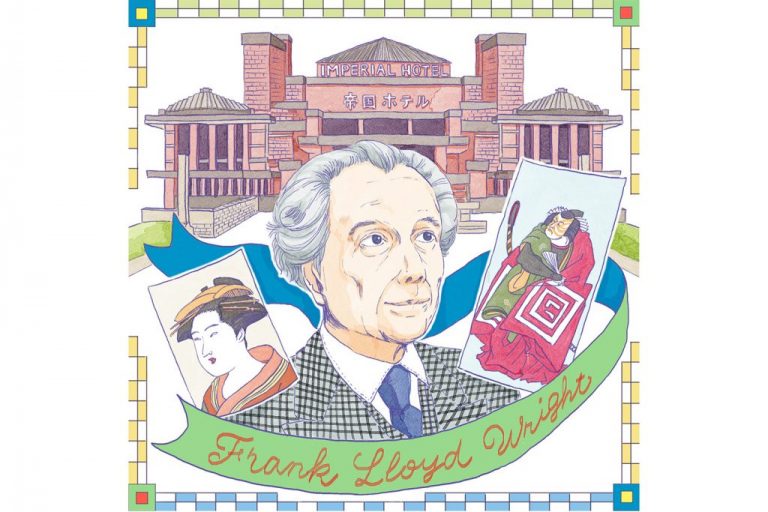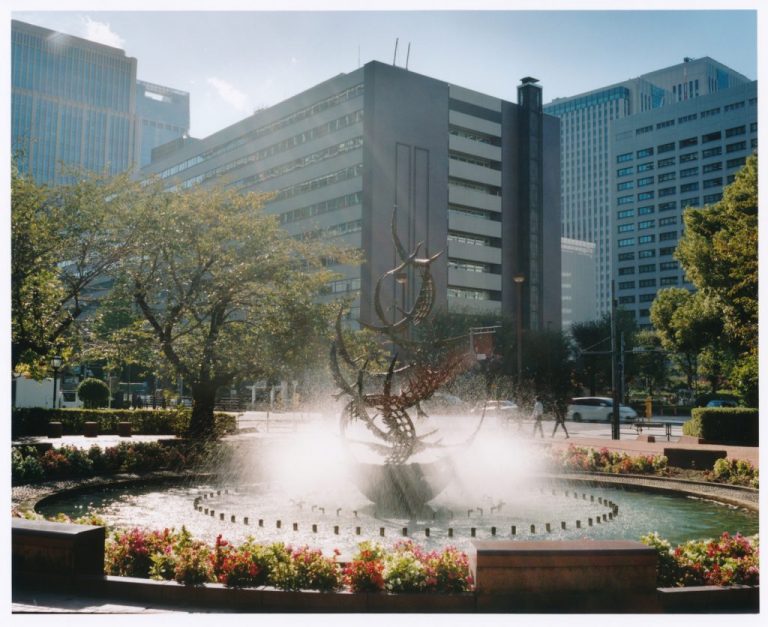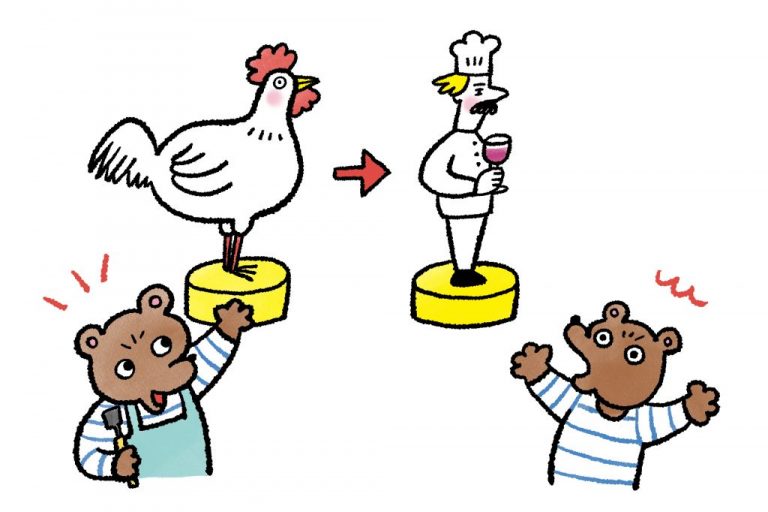本ご利用規約(以下「本規約」という。)は、公益財団法人東京都歴史文化財団(以下「当財団」という。)によって運営・管理される「Tokyo Art Navigation」(以下「本ウェブサイト」という。)をご利用いただくにあたって、本ウェブサイトの利用方法及び条件について定めるものです。
第1条 本ウェブサイトの目的
本ウェブサイトは、東京のアートシーンの”イマ”をご紹介することで、都民をはじめとする多くの方々に芸術文化に気軽に触れていただく機会を提供するとともに、東京を中心に活動するアーティストの創作活動を支援することを目的に制作された、東京の芸術文化に関する総合的情報サイトです。
東京を中心に活動しているアーティスト及び施設・イベント運営等でアーティストの創作活動を支援している方は、情報発信の場として、本ウェブサイトにアート作品やイベント・支援情報等をご自身で投稿することができます。
第2条 本ウェブサイトの利用
- 本ウェブサイトは、ユーザーに対して以下のサービスを提供します。
- 東京のアート・文化に関するコラム(記事)の提供
- 都内の博物館・美術館・ギャラリーなどの展覧会情報、劇場・ホール等での公演情報など、文化関連のイベント情報を投稿・閲覧できるサービス
- アーティストが創作した作品・活動等の画像・動画を投稿・閲覧できるサービス
- アーティストに向けたコンテスト・公募情報や支援情報を投稿・閲覧できるサービス
- 当財団は、随時、サービスの内容及び提供条件の更新、変更、その他本ウェブサイトの内容の全部または一部を更新、追加、中止、または変更することができるものとします。
第3条 定義
- 「ユーザー」とは、本ウェブサイトを閲覧またはご利用されるすべての方をいいます。
- 「メンバー」とは、東京を中心に活動を行っているアーティストの方及び創作活動を支援している施設・イベント運営等の方で、本規約を承認の上、投稿サービス等を利用するために「メンバー登録」を行った方をいいます。
- 「アーティスト」とは、アーティスト名を持って芸術文化の創作活動を行っている方をいいます。特に「TOKYO ARTISTS」でご紹介するアーティストは、創作活動の実績等を公表、もしくは芸術関連の学校や団体に所属されていることが確認できる方とさせていただきます。
- 「支援者」とは、文化関連の施設・イベント運営やコンテスト・助成等によって、アーティストの創作活動を支援されている方・組織をいいます。
- 本ウェブサイトの管理・運営は当財団が責任を持って行っておりますが、本ウェブサイト上の運用業務に関わることについては「TAN運営事務局」の名称を使用いたします。
第4条 本規約の適用及び変更
- 本ウェブサイトをご利用頂くユーザーは、適用される各規約の内容を理解しており、かつ、その全ての条項について同意したものとみなします。
- 当財団は、ユーザーの承諾を得ることなく、各規約を変更できるものとします。本ウェブサイトをご利用する際には、最新の各規約の内容をご確認ください。
- 当財団が各規約の変更を行った場合、当該変更内容および変更日を、本ウェブサイトに掲載して告知するものとします。
- 本規約の変更後、ユーザーが本ウェブサイトを利用した場合、ユーザーは本規約の変更に同意したものとみなします。
第5条 メンバーの登録情報について
- メンバーは、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
- メンバーとして本サービスを利用するためには、SNSアカウント及びメールアドレスによるアカウントを作成し「メンバー登録」を行う必要があります。また、「メンバー登録」には、以下の全てを満たす方であることを前提に、本規約で定める条件を満たすことが必要となります。
- 各規約に同意の上、継続して遵守できる方
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に一切関与していない方および関与している疑いのない方
- 過去に本ウェブサイトのメンバーとしての資格を抹消された経験がない方
- その他、当財団が不適切と判断する事由に該当しない方
- 当財団は、メンバーが本サービスを利用するにあたり、登録した個人情報や投稿情報等のメンバーに関する一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を取得するものとします。
- 当財団は、メンバーから取得する個人情報を、当財団が定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。ユーザーは、当該「プライバシーポリシー」に基づく個人情報等の取扱いに同意するものとします
- メンバーは、自己の責任において、正確な情報を登録するものとします。登録情報に変更が生じた場合には、直ちに本ウェブサイトが定める⼿続きにより修正しなければならず、メンバーは、登録情報を管理・修正する責任を負うものとします。
- メンバーからの投稿情報が、第6条の禁止行為に該当する、もしくは「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に則り青少年の健全な育成を阻害する恐れがあると当財団が判断した場合は、事前に通知することなく、投稿データを非掲載もしくは削除させていただきます。
- メンバーの登録情報に虚偽、誤りまたは記載漏れがあったことによりメンバーに損害が生じたとしても、当財団は一切責任を負いません。
- メンバーは、アカウント、およびパスワード等の管理に全責任を持つものとし、管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、当財団は一切の責任を負いません。また、アカウント等が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当財団に届け出るものとし、当財団からの指示に従うものとします。
- 当財団は、メンバーが第5条2項に反するもしくは第6条の禁止行為を行った場合、もしくは本規約のいずれかの条項に違反した場合、メンバーに何ら事前の通知または催告をすることなくメンバー登録を抹消することができるものとし、その効力は当財団による当該メンバー登録抹消手続きが完了した時点をもって生じるものとします。
第6条 禁止行為
ユーザーは、本サービスの利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 各規約に違反する行為
- 登録情報をはじめとする、その他一切の本ウェブサイトへ申告する情報を偽る行為または不備のある情報を申告する行為
- 他者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用等その他一切の権利または法的に保護される利益を侵害する行為
- 当財団または第三者になりすます⾏為、当財団または第三者との提携、協⼒関係の有無を偽る⾏為
- 公序良俗に反する行為(猥褻または暴⼒的なメッセージ・画像・映像・⾳声等を投稿、送信、掲⽰、発信する⾏為等を含みますが、これらに限られません)
- 犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為
- 本ウェブサイトにおいて事実に反した情報または架空の情報を提供する行為
- 本ウェブサイトの運営を妨げる行為
- 本ウェブサイトの利用に関連して、誹謗、中傷、脅迫、威嚇、悪態等、利用者としてふさわしくない言動や行為
- 当財団や本ウェブサイトの信用等を毀損する行為
- 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為
- 宗教活動、団体への勧誘行為
- 当財団への許可なく行われる広告、営業活動、営利を目的とした利用またはその準備をする行為
- 第三者の個⼈情報を収集、蓄積する⾏為
- アカウント等を第三者に譲渡もしくは貸与し、またはその他不正に使用する行為(第三者のアカウント等を使用して本サービスを利用する行為を含みますが、これに限られません)
- 迷惑メール、スパムメール等を開⽰、掲載、送信、頒布する⾏為
- 本ウェブサイトのサーバーに不正アクセスする⾏為
- コンピュータウイルス等の有害なプログラムやスクリプトを開⽰、掲載、送信、頒布する⾏為
- 本ウェブサイトにおいて使⽤されているソフトウェアまたはデータの全部または⼀部を複製、改変または⼆次利⽤する⾏為
- 本ウェブサイトやサーバー等に不正アクセスや大量のパケット送信をする行為
- その他、法令、政令、省令、規則、行政指導またはガイドライン・業界自主基準等(利用者が所在する国・地域のものを含み、以下「法令等」と総称します。)に違反する行為
- その他、当財団が本ウェブサイトにおいて禁⽌を告知した⾏為
- 前各号の行為を試みる行為、前各号に類する行為
- 前各号の行為に該当するおそれがあると当財団が判断する行為
- その他、当財団が不適切と判断する行為
第7条 著作権その他の知的財産権
- 本ウェブサイト上の文書や画像等の各ファイル及びその内容に関する著作権その他の権利は、当財団または本ウェブサイトのメンバーに帰属します。
- 本ウェブサイト上にアーティストから投稿された作品の著作権その他の権利は、投稿したアーティストに帰属します。当財団はアーティストが作品を投稿したことにより、アーティストが本ウェブサイトに及び公式SNSにおいて公開することに同意したものとして作品を公開します。
- ユーザーは、当財団や作品を投稿したアーティストの著作権その他の権利を侵害する行為を行った場合、当財団や作品を投稿したアーティストに対し、一切の損害を賠償する責任を負います。
- ユーザーは、本規約に違反して、本ウェブサイトのメンバー、ほかのユーザーまたは第三者との間で著作権その他の権利に関する紛争が生じた場合、自己の責任と費用により紛争を解決する責任を負い、当財団やその他ユーザーに何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第8条 本ウェブサイトに関する免責
- ユーザーが本ウェブサイトを利用される際は、内容の信頼性、正確性、完全性、有用性、適時性等について自ら判断するものとし、当財団はこれらにつき保証しません。
- 当財団は、ユーザーが本ウェブサイトを利用し、または、本ウェブサイトの内容の信頼性、正確性、完全性、有用性、適時性等に依拠して行ったいかなる行為の結果、あるいはユーザーの被る可能性のある損害について責任を負わないものとします。
第9条 免責事項
- 当財団は、次の事由によりユーザーに生じた損害について、その責を負わないものとします。
- 通信回線、インターネットサービス、通信機器、コンピュータ等のシステム機器等若しくは情報伝達システムの障害・瑕疵等、電気通信事業者、郵便機関若しくは金融機関等の第三者による通信の誤謬・遅延等、または、第三者による不正アクセス、情報の改竄、システム破壊、妨害等により生じた、本ウェブサイトにおける情報の消失、変質もしくは誤謬、または情報伝達の遅延、停止、中断、不能、誤作動等により生じた損害
- ユーザーが本規約の定めに従わなかったことによって生じた損害
- 本ウェブサイトを通じて提供する情報の誤謬、欠陥等により生じた損害であって、当財団の責に帰すことのできない事由により生じたもの
- 当財団の責に帰すことのできない事由により、アカウント登録情報、取引情報等が漏洩し、または不正に使用されたことにより生じた損害
- ユーザーが、本ウェブサイトを利用されることにより、当財団に損害等を与えた場合には、当該ユーザーは損害賠償責任を負うことがあります。また、ユーザーが、本ウェブサイトをご利用になることにより、他のユーザーまたは第三者に対して損害等を与えた場合には、当該ユーザーは自己の責任と費用において解決し、当財団には一切の負担または迷惑を与えないものとします。
第10条 協議
本ウェブサイトのご利用または本規約に関して、本規約により解決できない問題が生じた場合には、当財団とユーザーとの間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第11条 準拠法、裁判管轄について
- 本ウェブサイトの利用並びに本規約の解釈及び適用は、他に別段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。
- 本ウェブサイトの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、利用者は訴えを提起するための利用者に関する人的管轄権が、上記裁判所にあることに同意したものとします。
第12条 リンクの取扱について
- 本ウェブサイトから、もしくは本ウェブサイトへリンクを設定している当財団以外の第三者のサイト(以下「リンクサイト」という)の内容は、それぞれ各者の責任で管理されるものであり、リンクサイトの利用については、それぞれのサイトの利用条件や著作権等の規定に従ってください。
- 当財団は、リンクサイトの内容について、また、それらをご利用になったことにより生じた、いかなる損害についても責任を負いません。
- 本ウェブサイトへのリンクは、原則として自由です。リンクの際のご連絡は不要です。
ただし、トップページ(https://tokyoartnavi.jp/)以外のURLは予告なく変更する場合があります。
2021年9月30日現在